とっても古いスワッグの歴史

ヨーロッパでは、古くからクリスマスの定番飾り「リース」と共に、魔除け・幸福を呼ぶアイテムとして、暖炉や窓辺に飾るアレンジメントとして親しまれてきました。
けれど、スワッグがいつ頃からクリスマスの飾りとして親しまれるようになったのか、その歴史については意外と知られていません。
そこで、スワッグがクリスマス飾りとして定着した歴史について、ご紹介します。
スワッグの歴史は、なんと紀元前から始まった!
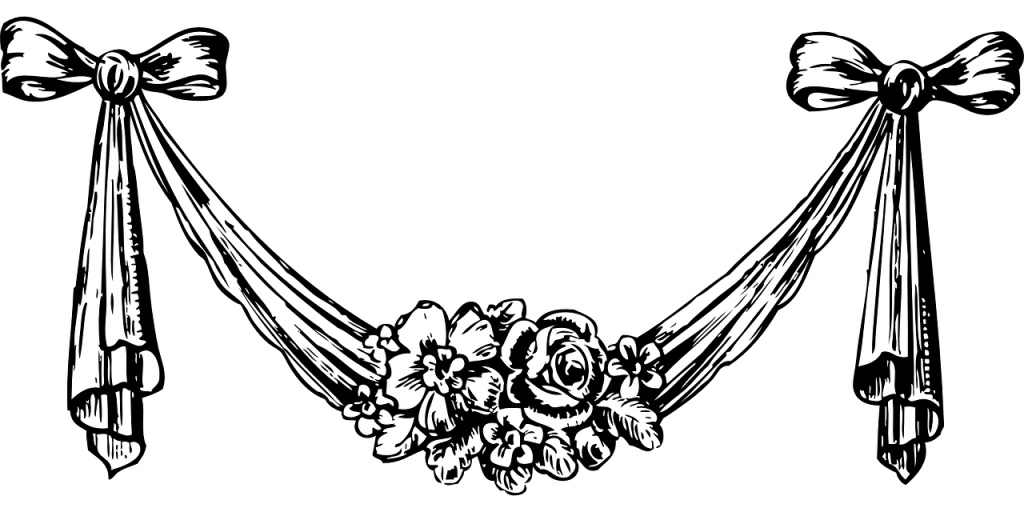
ドライフラワーを花束やブーケのようなかたちに束ねたボタニカルアレンジメント「スワッグ」は、ドイツ語で「壁飾り」を意味する「swag」のことであり、日本でもドイツ発祥のアレンジメントスタイルとして、広く知られています。
古代エジプトの時代には、お花や常緑樹の葉っぱを使ったガーランドやリース、サークレット、フェスツーンといった、スワッグによく似ているボタニカルアレンジメントが、死者を埋葬するときに手向けられていたそうです。
そのため、スワッグがドイツ発祥というのは、あくまで有力な説のひとつであり、詳しい歴史は未だ解明されていません。
ヨーロッパ地方に伝わるスワッグのアレコレ
日本で女性を中心に人気を集めているスワッグは、ブーケや花束のようなデザインをしたドライフラワーのおしゃれな壁飾りやタペストリーのことを指しますが、なんとイギリスでは、「スワッグ」ではなく「ハンギング・バンチ」や「スプレイ」と呼ばれていた時期もあったそうです。
ただ、言葉は時代と共に変化してゆくため、現在ではイギリスでも「スワッグ」と呼ばれ、リースと共にクリスマスを彩る飾りとして親しまれています。
クリスマス飾りの定番となったスワッグ

“森の国”と呼ばれるドイツでは、キリスト教以前から樹木信仰があり、冬至の日、おうちのなかに悪霊が入ってくるのを防ぎ、生命力に満ちた太陽の日差しを呼び込むため、常緑樹の小枝を戸口に吊るす習慣がありました。
この習慣が、いつしか“キリストの祝祭日に常緑樹の小枝を束ねておうちに飾ることは神聖なことである”となり、世界中に広まっていったそうです。
初めてスワッグがクリスマス飾りとして飾られたときは、マツの葉と実を赤いリボンで束ねただけのシンプルな飾りだったのですが、時代の流れと共に、多様な花装飾の良いところを取り入れながら、エレガントで華やかなスワッグへと進化しました。
これから先も進化を続けるスワッグ
スワッグの歴史に触れることで、飾ることの意味や込められた思い、願いを知ることができます。
これまで、単なるお部屋を彩るタペストリータイプのドライフラワーアレンジメントとして見ていた女性も、これをきっかけにスワッグを壁やドアに飾るときは、意味や思いなどを考えて飾ってみてはいかがでしょうか。




